モノサシ
こんにちは!
前回予告した通り、本日は自分なりに感じてきた感覚の違いの話をします。
これは、ガッツリの例え話なのですが…
例えば、ピンクという色を大多数の人が、ピンク色をちゃんとピンク色に見えていて、可愛い色だと感じていたとして、でも自分にはピンク色は赤色に見えていて、強そうな色だと感じていたとしたら、どうなるでしょう。 大多数の人は、戦隊もののリーダーに赤色を選び、自分だけがリーダーはピンク色じゃないの?と疑問を持ちます。
でも、その感じ方の違いは、相手の意識の中にでも入らなければ、分かるはずもなく、ピンク色をリーダーに選んだ自分は変わり者と呼ばれるのです。 まぁ自分は変わり者と呼ばれる事には抵抗がなく、というよりは寧ろ大好物です(笑)。
この、感覚の違いと、皆同じという思い込みこそが、すれ違いの根本に有るものだと自分は思います。
そして、それは周りにいる人全てお互いに言えることですが、中でも発達障がいの特性を持っていればなおの事、周囲の人にとっては理解しにくい存在に見えるのかもしれません。
そんな分かりにくい当事者である自分ですが、子どもの頃を振り返ると、確かに感覚をすり合わせるために無意識にしていた数々の事を少しだけ紹介します。
【優しい行動】
幼少期の体育の時間の記憶などほとんど残っておりませんが、ある瞬間だけは、今でも鮮明に覚えています。 それは、中学時代の体育の授業でドッジボールをしていた時の話です。 逃げ遅れて至近距離で転んでしまった子がいました。 自分は、何も考えず、至近距離にも関わらず、当たり前に思いっきりボールをぶつけて、その子を当てました。 ドッジボールなんだから、自分にとっては当たり前の事でした。 その後どうなったかと言えは、当てられた子の足は真っ赤なボールの跡が付き、目は涙でいっぱいになっており、なんだか居心地の悪い空気に包まれてしまいました。 後で考えれば、自分は陸上競技のボール投げの種目で学校代表で県のおれ大会に出るくらいには、肩が強かったので、 あそこまで強くぶつけることもなかったのかなと、後悔しました。 でも、ドッジボールはそんな場面にはよく出くわします。 その後悔を取り返す瞬間はすぐに来ました。 今度は同じことを繰り返さない様に、至近距離の相手には当てず、別の人を狙いました。 その時の周りの反応は、『優しいね』でした。 優しさとは、そういうものか…と強く意識したのを覚えています。 それからは、優しさは喜ばれることだと意識し、優しいと言われる行動パターンを情報として収集し、実行していたように思います。 そうして、自分は気付けば、『優しい人』と言われるようになりました。 しかも優しさの行動パターンに当てはめて行動しているので、感情は切り離され、誰に対しても同じ行動を取ってしまいます。 そんなに善人ではないのに、分け隔てなく優しくしてしまいます。 正直「優しい」と言われると違和感を感じてしまうのは、多分そのせいだと思います。
因みにですが…(ドッジボールの話に戻ります) 自分には多動・衝動性有りと診断されているので(診断は大人になってからですが)、至近距離の相手に対して、よくボールを当てずに堪えたなぁと感心しますが、勝ち負けに拘らずマイペースな自分の性格を考えると、ただ単に勝ちに興味がなかったからだと思います。 衝動性があるとは言っても、拘りがないところに対してはそんなものです。
【可愛いという感覚】
幼少期から、可愛いと呼ばれるものは、ぬいぐるみやリボンやキャラクターでした。 正直、可愛いという感覚は全然分からなかったので、可愛いもののカテゴリーを自分の中に作り、情報としてストックしていきました。
そんな幼少期を経ていたので、大学の時に出来た友人がメンズのシャツのデザインを可愛いと言っていた時は、かなり衝撃的でした。 そのシャツは、メンズのシャツなので全体的にはシンプルなデザインでしたが、明るい差し色のワンポイントがあるもので、そのデザインが好きか嫌いか聞かれれば、好きなデザインでした。 それからは、同じような感覚で好きなデザインを可愛いデザインとして、自分の中にどんどんストックされていき、いつしか可愛いデザインだと、自然に思うまでになりました。
そんな事を繰り返し繰り返し、少しずつ積み重ねて、40歳になってようやく、人に寄り添うという事がなんとなく分かってきたように思います。
分からない感覚を理解するという事は、本当にたくさんの経験が必要です。 その経験を得るためには、たくさんの失敗が必要です。 たくさんの失敗をするには、それを許してくれる環境が必要です。 何故なら、同じような失敗に見えても、本人にとっては同じじゃないからです。 人の何倍もの失敗をしてはじめて繋がって見えてくることも多いのです。 だから本当にたくさんの時間がかかるのです。 その経験を点と例えるとすれば、いつかその点は、線で繋がり始めます。 その点と点が線で繋がり始めれば、もうこっちのものです。 それまで腐らずに頑張り続けるかが重要で、その途中で心が折れてしまったら、自分の可能性にも気付かないままになってしまいます。 そんなのもったいないじゃないですか。
普通という曖昧なものを推し量る為に、人は基準を作ります。 その基準をそれぞれが持っているモノサシに例えるとすれば、100人いれば100通りのモノサシがあります。
モノサシは自分にとっては絶対的なものでも、他の誰かにとっては違うかもしれません。 その事を忘れた時に人はすれ違ってしまうのだと思います。
-1024x576.jpg)

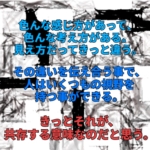
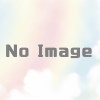
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません